スーパーCEO列伝
株式会社ユーザベース
チーフテクノロジスト
竹内秀行
写真/高橋郁子 文/箱田高樹(カデナクリエイト) | 2018.10.10


株式会社ユーザベース チーフテクノロジスト 竹内秀行(たけうち ひでゆき)
1981年生まれ。東京工業大学理学部情報科学科卒業。東京工業大学大学院情報理工学研究科中途退学。在学中はソフトウェア工学周りを研究。大学在学中から個人事業主として活動を始め、大学院在籍中に2社起業、うち1社を代表取締役として6年ほど経営。ハードウェアも含め、BtoB、BtoCのIT系サービスを数多く開発。2008年のユーザベース設立時からかかわり、「SPEEDA」のシステム面をつくり上げる。その後、チーフテクノロジストとして同社の技術面を牽引、「NewsPicks」および「FORCAS」の初期立ち上げを担当する。同時に複数社の技術パートナーとしても活動。2018年6月、「UB Ventures」のテクノロジー・パートナーに就任。
竹内秀行氏には、いくつかの“伝説”がある。その代表的なエピソードが、ユーザベースに参画する際の顛末だ。
2008年、「全く新しいBtoBの経済情報プラットフォームを起ち上げよう!」と稲垣裕介氏、梅田優祐氏、そして新野良介氏の3人が創業したユーザベース。もっとも、システム開発を担う優秀なエンジニア探しには四苦八苦していた。そしてようやくたどり着いたのが、稲垣氏の以前の職場の後輩の兄で、当時まだ東京工業大学に通いながらも企業のITシステムの受託業務を請け負っていた、スーパーエンジニアの竹内氏だった。
世の中に数多ある経済情報をわかりやすく、便利に見せる新しいBtoBのプラットフォーム「SPEEDA」をつくりたい。そんな同社のビジネスモデルと3人のビジョンを聞いた竹内氏は、こんなひと言と共にジョインしたという。
「面白そうなので、あなた方を助けてあげます」
いかにも天才らしい返答だ。しかし、本人に直接聞くと、あっさりとこの伝説は否定された。
「それね(笑)。僕は『助けてあげます』なんて言った覚えは全くないし、多分言ってないですよ。ただ……」と笑いながら竹内氏は言葉を続けた。
「『面白そうだ』とは確かに言った。そして僕が参画すれば必ずうまくいく、という自信もあった。彼ら3人と自分の力を“掛け合わす”ことができれば、いけると」

プログラマーの道へのきっかけをつくったのは父親だった。鉄鋼の研究者だった竹内氏の父親は、彼が3歳の頃から自宅のパソコンを自由に使わせてくれた。最初はゲーム。小学校に入る頃にはプログラミングの本も与えられた。マンガ形式のそれを読み、自らゲームをつくったのが、初プログラミングだったという。
「それからずっとパソコンには慣れ親しんできました。ただ、当時プログラミングはまだ開発環境が今よりも整っておらず難しくて途中で何度か挫折。あらためてプログラマーとして復活し、ソフトウェアの完成品をつくり始められたのは高1になってからですよ」
十分、早い。その後、高校の教室内に有線LANケーブルを這わせ、友達数人のノートPCを繋ぎ、授業中、内容をPCで入力する振りをしつつ、チャットシステムをつくるまでに。そして東京工業大学の情報科学科へ進学。20歳には個人事業主として様々な受託開発を始めた。その後、大学院に進学し数理・計算科学専攻でソフトウェア工学を学びながら、友人と共に案件を融通・協力しあうスタイルでシステムを受託開発する会社を興し、BtoB含め様々なサービスを手がけた。
「つくることと稼ぐこと」が重なる喜びがあった。その後、2つ目の会社も起業。そこでは院生ながら某企業のITシステムをすべて請け負った。
ユーザベースから声がかかったのは、この頃だ。「最初は自分の事業も利益は出ていたものの、行き着くところの限界も感じていたので他の道の1つとしてどうかな? という気持ちで話を聞きに行ったんです」と竹内氏は打ち明ける。
しかし、稲垣氏らのビジネスモデルとビジョンの“面白さ”に魅かれたのは先述通り。具体的に面白さを感じた理由は次の3つだったという。
1つは“金融にかかわる仕事”だったこと。大学時代から株やFXなどの投資を経験し、ダイナミックな資本の流れと企業の法人としての人生に強い関心があった。巷にあふれる様々な経済に関する情報を整理して、もっと使いやすくする意義が体感としてあったわけだ。
2つ目は“BtoBの確実性の高いターゲットを狙っていた”ことだ。想定顧客は潤沢な資金がある証券会社や投資銀行などの金融機関。そこに向け、ユーザベースが目指している使い勝手がいいウェブベースの企業・業界情報プラットフォームを提供すれば、顧客は飛びつくに違いないと踏んだ。エンジニアリングのみならず、すでに経営者の道を歩んでいたことが、こうした嗅覚を磨いていたのだろう。
そのうえで3つ目こそが、最も竹内氏を突き動かしたに違いない。創業メンバーの3人がしっかりとデータ集めやコンテンツづくりといった“「SPEEDA」にしかないコンテンツを集めること”にコミットしていたことだ。
「ユーザベース参画前までに、すでに多くのシステムをつくって実感していたのは、優れたシステムがあればいいサービスができるというわけじゃないということでした。たとえばどんなに優れたアルゴリズムを組み込んで完成されたシステムをつくっても、後から自分より優秀なエンジニアが出てきたらすぐさま追い抜かれる」
しかし、戦略コンサルや金融の世界でしのぎを削ってきた創業メンバーたちが、生きた経済情報のデータを集め、そこでしかつくれないコンテンツを実装する、というなら事情は変わる。
「優れたシステムに、優れた人の手でつくられたコンテンツを“掛け合わす”ことができれば、圧倒的な参入障壁になる。つまり勝てる」
こうして、2008年6月。竹内氏は“掛け合わせ”をはじめた。

「SPEEDA」は、世界中の企業情報、業界レポート、市場データ、ニュース、統計、M&Aなどあらゆるビジネス情報の収集、分析が可能なプラットフォーム。
丸一年かけて、竹内氏がつくり上げたプラットフォーム「SPEEDA」。その特徴は、何しろ使いやすく、分かりやすいことだった。
それまでも企業ごと、業界ごとの財務情報は、ネット上の有価証券報告書などで入手することはできたが、体裁は各社でバラバラ。網羅的な財務情報データベースも巷にあるにはあったが、時系列で瞬時に10年、20年スパンで並べたり、グラフィックで表示するような利便性はなかった。
「僕は形から入る人間なんですよ(笑)。言い換えると、まず使いやすさ。だから経済関連のサイトやサービス以外にも、他業種のサービスをベンチマーキングしてきましたね」
実は、このUX(ユーザーエクスペリエンス)の重要性を体現していることこそ、竹内氏がスペシャルである理由のひとつだ。美しいソースコードが手掛けられる。そんな凄腕エンジニアは多いが、しっかりとユーザー目線で“使い勝手の良さ”を重視した美しいシステムが手掛けられる人間はそう多くない。
「実は高校で本格的にプログラミングを学ぶ前に、DTP(デスクトップパブリッシング)を遊びでやっていたんです。運動会や文化祭のプログラムなどのデザイン・レイアウト、そして当時まだ走り出しだったDTPに対応している印刷所も少ない中、デジタル入稿までを担当していた。いかにコンテンツをわかりやすく、キャッチーに見せるためにデザインが大事か、ということを、このときに学べたと思います。そこで実践したことが、その後のエンジニア人生に影響しているのかも」
もちろん「仏つくって魂入れず」では意味がない。この使いやすいシステムには、“掛け合わせ”で、コンテンツが入る。

竹内氏がコードを書く一方で、創業メンバーの3人を筆頭にしたアナリストチームが、数多の企業や業界団体のデータをかき集め続けた。それらを基に「業界分析」「未来予測」などをはじき出したレポートを積み上げた。こんなオリジナルコンテンツが、使いやすく美しいテクノロジーに“掛け合わされた”ことこそが「SPEEDA」の本当の強みだ。
「だから、弊社サービスのプログラム、ソースコードをすべて公開しても、絶対に潰れない自信がある。そのままプログラムを真似されても、そこに掛け合わされている弊社独自のコンテンツがなければ、同じバリューが出せるはずがないからです」
手間暇かけてアナリストたちが集めたデータや、それらを基にしたレポートといった「SPEEDA」独自のコンテンツ。あるいは、竹内氏がその後、システム設計・初期の開発を手掛けた「NewsPicks」における、新たにジョインしてきたやり手の編集部員たちがつくりあげた記事コンテンツ。これらがなければ、魂のない仏像でしかないのだ。
裏を返せば、竹内氏が持つテクノロジーの知見に創業メンバーが“助けてもらった”ように、竹内氏も自らの知見を最大限に発揮するためには、創業メンバーを含むビジネスサイドのコンテンツの力、もっといえば、泥臭くデータを集める営業スキルが不可欠だったわけだ。
「やはりエンジニアとしては、世界中の人に使われるような価値あるプラットフォームをつくりたいという思いがあります。そのためには自分だけの力、エンジニアだけの力ではできない。それぞれのプロであり、多様性のあるチームだからこそ、実現できるんです。ユーザベースにはそれがありました」
だからこそ、竹内氏は2011年にはそれまでパートナーだった立場から、ユーザベースの社員に、そしてチーフテクノロジストになったわけだ。
「多様性を持つ組織は、エンジニアにとっては働きやすい場でもありますからね」
「テクノロジー×コンテンツ」「エンジニア×アナリスト」……。
そんな“掛け合わせ”の妙味がユーザベースの強さの源泉。だとしたら、掛け合わせる要素が増え、掛け合わせる機会が増えるほど、組織の強さも倍増していくはずだ。
「ユーザベースでは、エンジニアチームでもその環境だけにずっといるということはありません。たとえば全社ミーティングの中で話される経営陣の経営戦略を聞き、俯瞰的に理解したり、営業に同行してユーザーの声を丁寧に拾ったり……。結果、自ら手や頭を使う作業にフィードバックできるものって多いですからね。個々の視座を高め、モチベーションやスキルを向上させることにもなると思うんですよ」
こうした多様性を重視しているからこそ、社員全員が共有している価値観「7つのルール」が重要なのだという。
「特に最初に掲げられた“自由主義で行こう”が最重要ですね」
なぜか。多様な人間が集まるということは価値観も仕事のスタイルもバラバラな人間が集まるということ。ひとつの規律で縛り付けることは、到底ムリだ。多彩な個が、それぞれ最大限のポテンシャルを発揮するためには“自由に自律的に判断して働ける場であること”が最も合理的、というわけだ。
「だからエンジニアも働き方は自由です。何時に出社してもチーム内でちゃんとコミュニケーションが取れていれば、どこでどう仕事をしてもいい。多くのエンジニアにとって、すばらしく働きやすいと思いますね」
やけに強調するのは、竹内氏自身の経験が「自由主義で行こう」というルールづくりの素地になっているからだ。
「SPEEDA」開発時。ユーザベースにジョインしたあと、一時、作業の進捗を管理する目的で創業メンバーのひとりである梅田氏の隣の席に座らせられ、厳重な管理の下、プログラムを書かされたことがあった。みるみるやる気が削がれるのを感じたという。ついには「こんな縛られたやり方は僕には合いません。辞めさせてくれ」と直訴したという。
「これこそ半ば伝説のようになっていますが……本当のことですね(笑)。僕は周りに人がいる環境だと集中できないタイプ。もちろん逆に誰かとワイワイ……じゃないとできないタイプのエンジニアもいる。そんな多種多様な人それぞれが、最も心地よく働けるスタイルが“自由である”ということ。多様性を担保するための“自由”なんだと思います」
今は「SPEEDA」「NewsPicks」など、サービスごとのCTO(最高技術責任者)が立つようになり、竹内氏はさらに広く、グループ全体のテクノロジー関連の責任を担っている。同時に自由度は増し、中高生向けのプログラミングスクールなどを手掛けるライフイズテック社への“留学CTO”としてのジョインや、Excelでデータの可視化を目指す「E2D3」というアプリケーションのオープンソースプロジェクトへの参画など、社外活動も盛んだ。また直近では、個人会社でスタートアップ投資活動も始め、必要な資金を提供しつつ、逆に色々な情報や考え方を学んでいる。
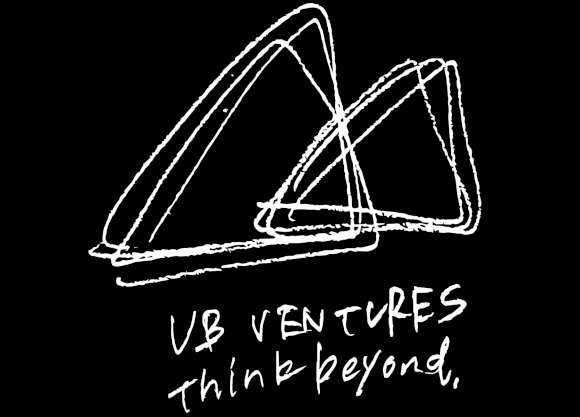
「UB Ventures」は「最後まで、船を降りない仲間でありたい」をメッセージとして掲げている。
さらに今年6月には新事業であるベンチャーキャピタル(VC)「UB Ventures」のテクノロジー・パートナーに就任。エンジニア目線で、新たな起業の芽を育む役割を担っている。
「最後まで、船を降りない仲間でありたい」。この言葉はベンチャーキャピタリストとして投資先に最後まで寄り添うという意味でつくられた。竹内氏はこのVC設立以前から、様々なスタートアップの話を直接・間接的に伝え聞く中で、途中で船を降りるCTOやエンジニアが極めて多いことに、非常に大きな懸念を抱いていた。
その実態こそがスタートアップのエコシステムの中で、他のすべてのCTOやエンジニアの立場を悪くし、上場・M&Aの際にエンジニアにお金がまわる仕組みが成立していない元凶になっているとも感じているという。
「日本では、ベンチャーキャピタリストで、ちゃんとエンジニア目線を持っている人は極めて少ない。僕が入ることで、技術面をしっかりと判断できるVCとしての立ち位置を極めたい。もっとも、やはり一番見るのはテクノロジーに掛け合わせる、優れたコンテンツや泥臭い営業手腕があるか、というところです。
そして、逆に技術はあるがコンテンツ面が足りておらず、絶対にサービスとして成立しない場合でも、どうコンテンツやデータを集めるのかを一緒に考えていきたいですね。
あと、可能な限りCTOやエンジニアに対してちゃんと事業の成功が還元されるよう、CEOやCTO・エンジニアへ提言していきたいと考えています。個人的には、エンジニアは3年に一度転職し他の技術ややり方に触れるべき、と言っていたりするのですが、どう折り合いをつけようかなと悩んでいたりします(笑)」
テクノロジーのブラッシュアップ、新しい働き方の提案、そしてインキュベーション――。自由に翼を広げた天才エンジニア。ほうぼうで新たな“伝説”を生み出していくに違いない。

vol.56
DXに本気 カギは共創と人材育成
日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社
代表取締役社長
井上裕美


