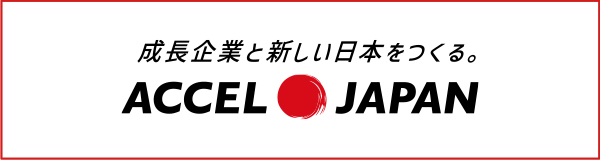小笠原流人生戦略研究所
代表
小笠原 広志
撮影/芹澤裕介 文/竹田 あきら(ユータック) 動画/プログレス | 2021.01.12


小笠原流人生戦略研究所 代表 小笠原 広志(おがさわらひろし)
1971年大阪に生まれ、滋賀県で育つ。製造工場向けの人材派遣会社で、現場責任者として取引先の拡大に貢献。キャリアコンサルタントの資格を得て、社内コンサルタントとして派遣社員のキャリア形成を支援。2020年10月に「小笠原流人生戦略研究所」を創業。「人と経営」の本質に向き合い活性化させる支援を行っている。
セルフ・キャリアドックとは、社員のキャリア形成をバックアップするために、企業が導入する一連の仕組み。キャリアコンサルティング面談とキャリア研修を組み合わせ、社員の自発的なキャリア形成を促そうとする取り組みで、2016年の職業能力開発促進法の改正に伴い厚生労働省が推奨するキャリア開発支援だ。
「セルフ・キャリアドックの導入には、国家資格である『キャリアコンサルタント』や、『技能検定キャリアコンサルティング職種(1級・2級)』の有資格者を必要とします。社内の人材に資格取得をさせて独自に進めるケースもありますが、そうすると人事評価の延長線上となってしまい、健全なキャリア形成が阻害されてしまいます。社外コンサルタントに依頼すれば社員が本音を言え、キャリア形成がスムーズに進みます」
反対に、セルフ・キャリアドックを導入することで社員が自分のキャリアを主体的に考えるようになり、その結果「転職する」「自分勝手な仕事をする」といった懸念を感じ、セルフ・キャリアドックに懐疑的になる経営者も少なくないという。しかし、セルフ・キャリアドックを導入することで企業の業績が伸びると、小笠原代表は指摘する。

「キャリアコンサルティングやキャリア研修で『社員の自発性』を掘り起こしていきます。それまで受け身の姿勢で仕事をしていた人材が、仕事を前向きにとらえるようになり、自発的に動く人材へと生まれ変わります。そうすれば、業務が効率化され、社内にイノベーションも生まれます。中小企業の中にはセルフ・キャリアドックを否定的にとらえる企業もありますが、人材不足に悩む中小企業こそセルフ・キャリアドックを導入すべきです」
小笠原代表は、前職の人材派遣会社で長年、工場での現場マネジメントに携わってきた。だからこそ、現場で働く人の思いや考えを知っており、マネジメント側である経営者の苦労も深く理解している。

キャリアコンサルタント養成講座で受講者を支援する立場として活躍する小笠原代表。
「コンサルティングや研修・セミナーでは、社員の話を徹底的にヒアリングして、どんどん質問を投げかけ、自らの頭で考えるように促します。自分の頭で理解すれば、自発的に目標を設定して意思決定をし、あれこれと工夫をする人材に変わります。キャリア形成の第一歩は、“自分の仕事の本質”を理解することです」
キャリア形成を意識した働き方を企業がサポートすることで、若手社員の離職を防ぎ、中堅・シニア社員のモチベーション維持にもつながる。
「キャリアコンサルティングを通して仕事をする上での悩みを聞き出し、アドバイスをすることで『心の健康』を維持して、良好な人間関係を構築できます。目の前の仕事に忙殺される日々を見直して人生の目標設定をすることで、豊かな人生を送れるようになります」
同じカテゴリーの経営者

vol.56
DXに本気 カギは共創と人材育成
日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社
代表取締役社長
井上裕美