スーパーCEO列伝
株式会社 幻冬舎
代表取締役社長
見城徹
文/長谷川 敦 写真/宮下 潤 | 2019.10.10


株式会社 幻冬舎 代表取締役社長 見城徹(けんじょう とおる)
1950年12月29日、静岡県生まれ。慶應義塾大学法学部卒。大学卒業後、廣済堂出版に入社。初めて自身で企画した『公文式算数の秘密』が38万部のベストセラーに。1975年、角川書店に入社。「野性時代」副編集長を経て、「月刊カドカワ」編集長に就任、部数を30倍に伸ばす。5本の直木賞作品をはじめ数々のヒット作を生み出す。
1993年、角川書店を退社し、幻冬舎を設立。五木寛之『大河の一滴』、石原慎太郎『弟』、唐沢寿明『ふたり』、郷ひろみ『ダディ』、天童荒太『永遠の仔』、村上龍『13歳のハローワーク』、劇団ひとり『陰日向に咲く』、長谷部誠『心を整える。』、渡辺和子『置かれた場所で咲きなさい』など25年間で24冊ものミリオンセラーを世に送り出す。著書に『編集者という病い』(太田出版)、『たった一人の熱狂』(双葉社)、『読書という荒野』(幻冬舎)、サイバーエージェント代表取締役社長・藤田晋氏との共著に『憂鬱でなければ、仕事じゃない』(講談社)、『絶望しきって死ぬために、今を熱狂して生きろ』(講談社)、松浦勝人との共著に『危険な二人』(幻冬舎文庫)、林真理子との共著に『過剰な二人』(講談社)などがある。
――今日は見城社長がさまざまな作家やアーティストとどのように関係を築きながら、数々のベストセラーを生み出していったのか。そんな話を伺いたいと思っています。
見城 うーん……あんまり好きじゃないんだよね、そのテーマ。
だって人間関係なんて、作ろうと思って作っているわけじゃないからね。やむにやまれぬ生き方をしてきた結果、そういう関係になっていくだけなんだよ。
「人脈」という言葉も嫌いです。人脈を作ろうとしてパーティや人脈交流会にいっぱい出ても、そこでできた関係なんて表面的なもので、大切な仕事には何ひとつつながらないからね。
決定的な仕事をしなければ、人間関係なんてうまくいかない。相手が困っていたり頼んできたときに、自分が無理だ、きついな、しんどいなと思うことをやらなければ、相手はありがたいとは思わない。それを日常的にやってさえいれば、儀礼的なことや表面的なことは必要ありません。
だから僕はパーティにはめったに出ない。年賀状も出しません。手紙はその人に対して書きたいと思ったときに書けばいいわけだから。形式的に年賀状を出したって、意味がないと思うんです。

――お世話になっている作家さんにも年賀状は出しませんか。
見城 出さないです。
――それで関係が壊れることはない?
見城 年賀状を出さないせいで壊れる関係なんていらないですよ。
そんなことよりもその作家が作品を出したときに、ちゃんと読んで、血のにじんだ感想を手紙にしたためて送ったほうがずっと相手の心に響くじゃない? 僕は大事なことを伝えたいとき、いつも手紙を書いている。それをやっている限りは、年賀状なんて必要ありません。
例えば、角川書店に入社して文芸誌「野性時代」に配属になったとき、学生時代から憧れていた五木寛之さんとどうしても仕事がしたいと思った。でも五木さんはそれまで角川から新作を出したことはありませんでした。
そこで僕は五木さんが長編小説を出版したり、短編を発表したり、エッセーが掲載されたりするたび、そのすべてを読み込んで、感想を五日以内に書いて手紙で出すことを続けたんです。そして25通目を出したあと、ようやく五木さんにお会いすることができました。
そこからは早かった。「どうしても五木さんと仕事がしたいんです」という僕の言葉に、五木さんは「うん、やろう」と短く答えてくださいました。僕の思いは25通の手紙を通じて、すでに五木さんの心に届いていたからね。

五木寛之さんと見城社長。
――松本清張さんと最初にお会いしたときは、百数十冊ある作品を全部読んでから臨んだそうですね?
見城 もともとある程度は読んでいた上に、あらためて読みました。お会いしたときにどの作品の話が出ても、ちゃんと感想を言えるようにするためです。結局、作品の話など出なかったけどね。でもそこまでやらないと、相手の心の中に自分の手跡をつけることなんてできないよね。
圧倒的な努力というのはそういうものですよ。僕は、その場しのぎ、小手先、帳尻合わせ、上っ面というのが大嫌い。パーティに出たり、年賀状を出したりすることを圧倒的な努力とは言いません。
――角川書店に入ったときは「『角川では書かない』と言っている作家だけから原稿をもらう」ことを自分へのルールとして課したそうですね。五木寛之さんは、まさにそうでした。なぜそんな大変なことに、あえて取り組もうとしたのでしょうか。
見城 そうじゃなければ僕の存在価値がないからですよ。
「角川書店です」と会社の看板を言えば、喜んで書いてくれる作家は当時からたくさんいた。でもそういう仕事は誰でもできる。人と同じことをやっても僕がそこにいる意味がないわけだよね。
周りが「無理だ」「不可能だ」と思っていることを可能にしていかないと、圧倒的な結果を残す仕事はできません。
「無理」というのは理が無いと書きます。しかし、理があることはできて当然。理が無いこと、つまり無理を通してこそ、初めて結果を残す仕事ができるんです。

角川書店時代の見城社長。角川本郷ビル前で。
――自著『読書という荒野』では、「石原慎太郎さんには『このテーマで書いてもらえばベストセラー間違いなし』という3枚のキラーカードを常に用意していた」と書かれていましたね。
見城 石原さんだけに限った話じゃないです。「一緒に仕事がしたい」と思っている作家やアーティストに対して、僕は常に3枚のキラーカードを用意しています。
――3枚ある意味は?
見城 3枚ぐらいないとダメでしょう。
状況に応じて出すべきカードも違ってくる。こっちが「あなたはこれを書くべきだ!」と切り出したとき、相手がたまたま不機嫌だったりして、そのテーマを新鮮に感じてもらえなければ、元も子もなくなる。
だから一緒に食事していても、ゴルフをしていても、旅行をしていても、常に相手のことを見ている。「3枚あるどのカードを、いつ切るのがベストか」という機を見計らっています。

石原慎太郎さんと見城社長。
――石原慎太郎さんには、どのようなカードをどう使われたのでしょう?
見城 3枚のキラーカードのうち1枚は「弟の裕次郎について書いてほしい」でした。
これは石原さん自身も書きたいと思っていたみたいで、僕が「書いてください」と言ったら、即座に「書く」と言ってくれたけれどもね。『弟』(1996年)という作品として結実しました。
2枚目は「老残」です。老いていく悲しみや醜悪さ。『太陽の季節』(1956年)というエネルギーの満ち満ちた若者を主人公として描いた作品で颯爽とデビューした作家だからこそ、書くべきだと思ったんです。
ところが石原さんは「俺には老いはない。老いを迎え撃つ」って言うんだね。老いを迎え撃つのだったら文学にならないから、エッセーにするしかない(笑)。これが『老いてこそ人生』(2002年)という本です。
3枚目のキラーカードは「政治」です。文学者が政治の世界に行ったんだから、その苛酷さを書かなければダメだ。文学は観念でいいけれど、政治は現実だからさ。現実は、善だけで構成されているわけではないから悪にも手を染めるわけだ。それを書かせたかった。
本当は「大物政治家の中川一郎がなぜ自殺したかを書いてほしい」と話しました。彼は中川派の若頭として、中川一郎が死に追い込まれたときを間近に見たわけだから。ところが石原さんは「俺はそのことについては、墓場まで持っていく」という。そして代わりに書かれたのが、田中角栄元首相を描いた『天才』(2016年)だった。



『弟』 (幻冬舎文庫)
『老いてこそ人生』(幻冬舎文庫)
『天才』 (幻冬舎文庫)
――『弟』『老いてこそ人生』『天才』。3冊ともミリオンセラーになりました。
見城 だから完勝ですよ。
ただ石原さん本人は『弟』以外2冊は「自分が書くべきだ」と気づいてもいなかった。編集者は表現者に対して、相手が思ってもいなかったこと、考えてもいなかったことを、言葉にして相手に伝え、新たな気づきをもたらすことができる人間でなくてはいけないんですよ。
そのためには、相手が作家であればその書いたものをちゃんと読み、ミュージシャンであればその音楽をちゃんと聴き、俳優であればその舞台や映画を徹底的に観ることです。
そこまでやった上で「あなたはこれを書くべきだ」と言える。また、だからこそ相手は「見城という人間は、誰よりも自分の作品を理解してくれるヤツだ」と思ってくれ、「書くよ」と言ってくれるわけですよ。
――そこまでやっているから、書き手側も「見城さんと仕事をすれば、新たな作品世界を切り拓けるかもしれない」という気になる。
見城 そう思わせられない編集者はダメですよ。どんな仕事も一緒なんじゃないですか? 正面突破以外に方法はないんだよ。

――五木寛之さんとは、『大河の一滴』というミリオンセラーを世に出されました。
見城 あれはある意味偶然から生まれた作品でした。ある夜、五木さんと東京プリンスホテルのピカケというティーサロンでお茶を飲んでいた。今から20年数年前だから日本が経済的にも政治的にも社会的にも行き詰まっていた時期。五木さんが珍しく説教じみた口調で「こういうひどい時代に人はどう生きればいいのか」と中国の屈原(くつげん)の故事を持ち出して話し始めたんですよ。「見城君、人というのは、そんなに清廉潔白には生きられないものなんだよ」って。
その五木さんの言葉が、僕の心に染み込んできて、思わず身を乗り出して「五木さん、その話を書いてください。絶対に今書くべきです」と言ったんだ。それに応えてくれた五木さんが書いたのが『大河の一滴』なんです。
あの作品は、あの日五木さんと一緒に飯を食わなければ生まれなかった。そのあと一緒にお茶を飲まなければ生まれなかった。さらにいうなら25通の手紙から始まった僕と五木さんとの関係があったから生まれた。すべて偶然だったけれど、必然だったんですよ。
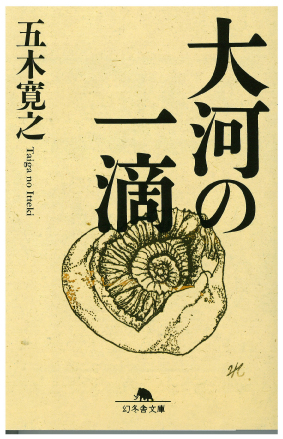
『大河の一滴』(幻冬舎文庫)
――最近では、歌手の浜崎あゆみさんとエイベックス代表取締役会長CEOの松浦勝人さんとの恋愛を描いた『M 愛すべき人がいて』(小松成美・著)を見城社長ご自身がプロデュースし、ベストセラーとなっています。
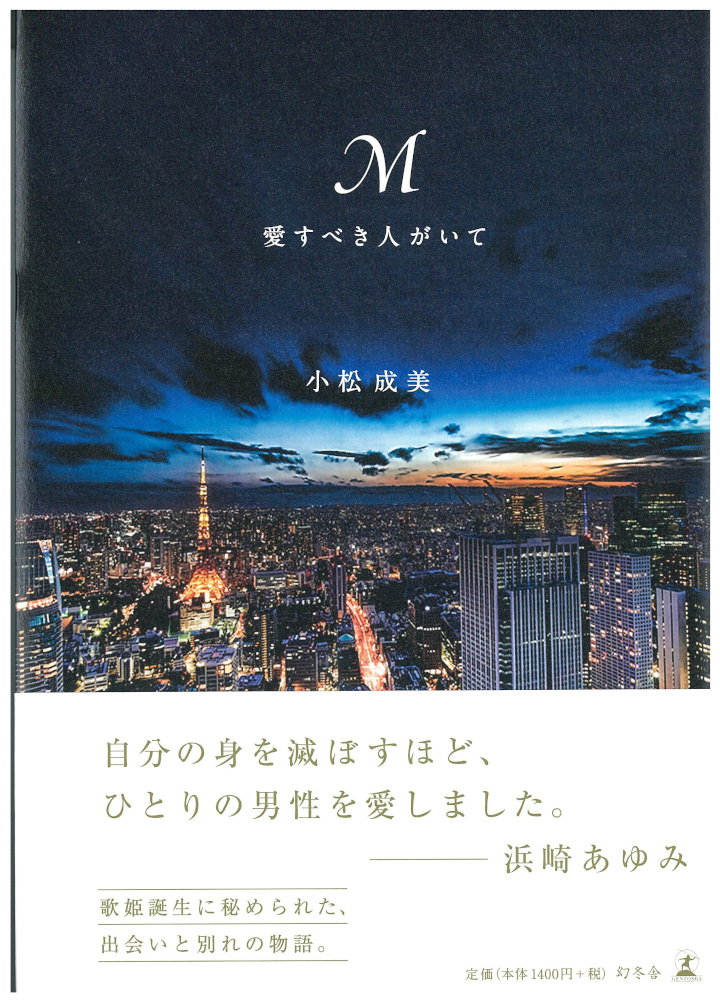
2019年8月1日に発売された『M 愛すべき人がいて』は、発売と同時に大きな話題を呼び16万部を突破。
見城 あれも松浦勝人や、サイバーエージェントの藤田晋との20年来の関係があったから、作り上げることができたもの。彼らとはお互いにわがままを言い合ってきたので、「藤田が言うのならしょうがないな」「松浦が言うのならしょうがないな」「見城が言うならしょうがないな」というのがある。
藤田はAbemaTVで、決定的な話題作となるドラマをずっとやりたかった。そんなときに松浦と浜崎あゆみの3人で飲む機会があって、「2人のかつての恋をドラマにしよう」という話がまとまったわけだ。飲み話の中でね。で、藤田が俺のところに電話をかけてきて「こういう本を作ってくれませんか。作ってくださったら、ぜひドラマにしたいんです」と言うんだ。
最初は話半分に聞いていました。だって浜崎あゆみにしても松浦にしても相当なリスクがある話だし、これが日の目を見るためにはかなりの紆余曲折を経ることが、誰だってわかるからね。
でも一方で「これができるのは俺しかいない」とも思った。

――見城徹しかできない仕事だと。
見城 そう。彼らと心からつながり、リスクも負える覚悟がある人間は他にいない。松浦に「本当にいいのね?」と確認したら、「できればやりたい」と言うので、覚悟を決めたんです。
ノンフィクション作家の小松成美を著者に選んだのは、取材力があって、しかもちゃんとラブストーリーに仕上げられる書き手は誰かと考えたときに、小松しか浮かんでこなかったからです。
まあ大変だったけどね(笑)。藤田が僕に電話をかけてきたのは昨年の8月1日。いろんなことがあって、ようやく「これは出版できるかもしれないな」と思ったのは、6月末ぐらいのことです。原稿はすでにできていた。でもそれを彼らがそのまま通してくれるかどうかわからなかったからね。何回かのゲラチェックを経て、本が発売されたのは偶然にも1年後の8月1日だった。
――彼らに原稿チェックをしてもらったときも、なるべく直さないでくれと?
見城 全編そうですよ。「ここは直さないでほしい、これも直さないでほしい」って。でも向こうは直したい。リスクを少しでも軽くしたいからね。その戦いでした。
浜崎あゆみには冒険だったと思います。「あの頃私が書いていた歌詞は、松浦さんに自分の想いを伝えるためのものでした」と告白した瞬間に、読者は「そうなの?」となって、普遍性を無くすわけだからね。でも作品なんて、最初は全部個人的な想いから始まるものですよ。それが多くの人の心を打つから、普遍性を持った作品になっていくんです。
ただそうは言っても、自分がどんな思いで歌詞を紡いでいたのかの内実を全部明らかにされるのは、浜崎にとってつらかったと思います。松浦は松浦で家庭があるし、やはりつらかったでしょう。
でも、誰も傷つかない“なあなあ”の作品にしてしまったら、大したものにはならないですよ。だから「それはダメだよ」と言い続けたんです。これを僕が最後まで押し通せたのは、やはり僕が松浦や藤田と根本的な付き合いをし続けて、強いつながりがあったからですよ。

左から見城社長、松浦会長、藤田社長。
――人のために骨身を惜しまない見城社長が「この人と仕事をしたい」と思いながらもつながりを築けなかった相手はいない?
見城 いや、それはいるよ。いますいます。山崎豊子さんには何度も何通も手紙を書きました。もうこれ以上書けない、というほどの渾身の手紙を書いた自負もある。けれど、「新潮と文春以外からは出さない」とその壁を崩せなかったね。
村上春樹さんもそうだ。『風の歌を聴け』(講談社)を出したすぐあとに、すばらしい作品であることを伝えたくて「あなたの作品を僕はこういうふうに分析している」と伝えた。しかし、彼の意にはそぐわなかったようで、それきりの関係に。一度だけ雑誌に小説を受け取ったことはあるが、本をつくることはかなわなかった。村上春樹と本をつくりたかった、という思いはあるよ。
うまくいかなかったことはたくさんある。ただ記憶に残らない。歴史に残らないんだ。そういうことなんですよ。

――見城さんは編集者であると同時に、経営者でもあります。編集者と経営者とでは、求められる能力は違いますか。
見城 まったく違います。編集者は惚れ込んだ作品に対して、遮二無二突き進んでいかなくてはならない。けれど経営者は視座を高めてポートフォリオを組んで、安全策まで講じられなくてはいけない。ベクトルがまったく逆だよね。
――でも見城社長の作家や作品へのかかわり方を見ると、常に遮二無二突き進んでいるように思えるのですが。
見城 闘っているんだよ。編集者の見城と、経営者の見城が。
天童荒太の『永遠の仔』(1999年)のときもそうだった。あれは今、幻冬舎の専務をやっている石原正康が担当編集者として手がけた作品だったけど、ゲラで読んだときにあまりにも素晴らしかったので「この作品は大量の広告を打とう!」と決めて、25万部は売れないとペイできないぐらいの広告費を注ぎ込みました。
そのときは編集者の見城が経営者の見城を「これは絶対にミリオンセラーにできる作品だから、勝負しなければダメだよ」と説得したわけですよ。
経営者は安全策も大事だけど、大きな結果を残すためには、時には賭けにも出なければいけない。編集者の見城が「絶対にいける」と言うんだから、これはいかないわけにはいかない。結果は160万部を超えるミリオンセラーになりました。
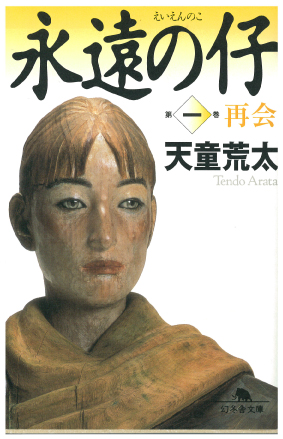
『永遠の仔〈1〉再会〉』(幻冬舎文庫)
――編集者の見城と経営者の見城は、共存できるものなのですか。
見城 いつも夜中に怖くなりますよ。経営者の見城が「あんなに刷って大丈夫か……」って。
郷ひろみの『ダディ』(1998年)を出したとき、初版を50万部刷ったんです。もし50万部刷ったうちの30万部が売れずに返ってきたら、確実に倒産でした。
周りからは言われましたよ。「見城さん、5万部刷って売れたら増し刷りしていけばいいじゃないですか」って。
でもそんなやり方は、僕には意味がない。初版50万部を刷ってあっという間に売り切れるから、世の中に鮮やかな印象を残せる。5万部から始めていたら、せいぜい20万部しかいかない。初版50万部から始めたから、1週間で100万部に達したんです。鮮やかにやるためには、リスクを取るしかないんです。
ようは眠れないほどの怖さを抱くくらいじゃないと圧倒的な成果なんて出せない。不安や恐怖が無いということは、その程度の仕事しかやっていないということなんだよ。

――不安や恐怖は、むしろ推進力でもあると。
見城 だから僕はボクサーが好きなんだ。
彼らは常に不安や恐怖と戦っている。「俺は次の試合では、1ラウンドでマットに這いつくばってしまうかもしれない」。しかし、そんな恐怖感が、彼らを徹底的なトレーニングに向かわせるわけだ。
僕も圧倒的な恐怖感がある。だから、圧倒的な努力を続けられる。そしていつも怖がりながら挑戦したい。何度でもリングに上がりたいんですよ。

vol.56
DXに本気 カギは共創と人材育成
日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社
代表取締役社長
井上裕美


