スーパーCEO列伝
ライフスタイルアクセント株式会社
代表取締役
山田敏夫
文/杉山 直隆 写真/宮下 潤(インタビュー、商品) | 2020.08.11


ライフスタイルアクセント株式会社 代表取締役 山田敏夫(やまだとしお)
1982年生まれ。熊本県熊本市出身。創業100年を超える老舗婦人服店の息子として育つ。大学在学中、フランスへ留学しグッチ・パリ店で勤務して一流のものづくり、商品へのこだわり、プロ意識を学ぶ。2012年1月、工場直結ジャパンブランド「ファクトリエ」を展開するライフスタイルアクセント株式会社を設立。年間訪れるものづくりの現場は100を超える。著書に『ものがたりのあるものづくり ファクトリエが起こす「服」革命』(日経BP社)がある。
「この白いコットンパンツはすごいですよ。醤油やコーヒー、ワインをこぼしても何でも弾く。岡山県児島のレッドリバーという工場でつくっていて…」
「『“座る”を快適にするパンツ』を、デサントの村岡工場と開発しました。村岡工場は大谷翔平選手も使っている野球ユニフォームの専門工場で、そのノウハウを活かした…」
「これは10年間使えるカシミヤのマフラー。むしろ使えば使うほど柔らかく、使い心地がよくなるマフラーなんです。岩手県のすばらしい工場があって…」
熱をこめて語る商品の数々。すべて山田敏夫氏が立ち上げたファクトリーブランド「ファクトリエ」の商品だ。

ファクトリーブランドとはメーカーではなく、普段その仕事を請け負う工場が独自に立ち上げたブランドのこと。「ファクトリエ」では、日本各地の工場と共同で開発した商品を中心に自社サイトで販売している。中間業者が入らないため、質の高い商品を適正価格でユーザーに届けられるわけだ。
しかも契約する55の工場は、同業他社にも一目置かれる技術力を持った一流の国内工場ばかりだ。パリやミラノにある世界的な老舗高級ブランドのシャツやニットを製造する工場も多い。山田氏が700もの工場を見学し、選び出したと言う。


デサントの村岡工場と開発した「“座る”を快適にするパンツ」。
岩手県のニットメーカー UTOがつくる、10年先まで「育てるホワイトカシミヤマフラー」。
そんな工場のポテンシャルを最大限に発揮してもらうため、山田氏は「思う存分つくりたい商品をつくってほしい」と商品企画や値付けを任せる。だから、品質は折り紙付き。ワイシャツ1枚とっても、生地から縫製、パターンなど、あらゆる面から職人の技術の粋とプライドを感じられる。
「このような、思わず誰かに語りたくなる高品質な商品を、お客様のもとに適正価格で届けることで、作り手もお客様も僕らも幸せになる。こうして『語れるもので日々の生活を豊かに』することが、僕たちのミッションです」(山田氏。以下同)
創業から8年、今ではこうした商品づくりに共感した熱いファンを数多く獲得している。昨今のコロナ禍において、アパレル各社の苦境が伝えられているが、「ファクトリエ」は、2020年4月の緊急事態宣言以降も、売上が前年比を超えている(※2020年7月現在)。

工場とのコミュニケーションを深める「工場文化祭」を毎年開催。写真は2019年開催時のもの。
「工場に応援メッセージを送れる仕組みがあるのですが、緊急事態宣言後の1ヶ月で約6000件のメッセージが寄せられました。応援の意味で商品を買ってくださっているお客様もいるようです。一種の『応援経済』ができつつあります」
もっとも道のりは平坦ではなかった。ファッションブランドが自社製品の生産工場を前面に出すことは、日本のアパレル業界で歓迎されなかったからだ。
とくに高級ブランドの製品を生産する工場は「ブランドイメージを壊してほしくない」と守秘義務を求めることも少なくない。工場側も安定収入を捨ててまで自社ブランドをつくる必要性がなく、“黒子”でよしとする面がある。
その状況を打開できたのはなぜか。山田氏が発する「熱」が、工場や従業員たちの心に火をつけたからだ。
「お客様にしても協力してくれる工場にしても、僕らの心の内側が熱狂していなければ、必ず相手に見透かされます。まずは自分たちが熱狂する。その余熱が外ににじみ出るほどにならないと、大勢を巻き込むことはできませんよ」

「ファクトリエ」に賛同し、顧問を務める元エルメス本社副社長の齋藤峰明氏と。
そもそもこのビジネスを立ち上げた原点は、大学在学中の2002~2003年にフランス留学をしたことだ。
熊本の実家が洋品店を営んでいた山田氏は「ファッションを学ぶ」ため、フランスに留学。パリのサントノレ通りにあるグッチの旗艦店でアルバイトを経験し、工房から出発したグッチのものづくりに対する矜持を目の当たりにした。一方で、フランス人の同僚に言われた一言が強く心に残ったと言う。
「『日本には本物のブランドがない』と言われたのです。織物や染め物など数百年以上の歴史を持つ技術があるのに、衣類はメイド・イン・チャイナばかりじゃないかと。『ものづくりから生まれた、メイド・イン・ジャパンのファッションブランドはあるのか』と聞かれると、返す言葉がなかった」


パリ留学時代、グッチ・パリ店のスタッフたちと。
子供時代、1917年創業の実家の老舗婦人洋品店にて。
友人と観光に出かけたシャンパーニュ地方でも衝撃を受けた。彼の地にはぶどう農家が多々あり、世界で最も知られた発泡酒「シャンパン」の原料を多くつくっていた。そして彼らの平均収入はフランスで一番高く、極めて仕事に誇りを持っていたからだ。
「つくり手が儲かって買う人も幸せ。そんな世界が本当にあるのか、と思ったのです。日本はというと、農業でもアパレルでもつくり手こそが儲からない現状があった。たとえば熊本は農産県で、スイカの生産量日本一ですが、スイカ農家がお金持ちかというと何ともいえません。この違いは何だ? と」
この経験から、山田氏は次のような夢を思い描いた。「世界に通用するメイド・イン・ジャパンのファッションブランドを生み出す」こと。そして「日本でも、つくり手が儲かって、買う人も幸せな世界をつくり出す」ことだ。

当初は具体的な事業イメージが描けず、大学卒業後8年間は求人広告の会社で働いたり、アパレル通販サイトでアルバイトをしたりしていたが、2012年に「天・地・人」の3要素が揃ったことで、事業イメージが明確になった。
「天は『スマホと高速通信回線の普及でネット通販がしやすくなった』こと、地は『LCC(格安航空)の登場で、地方の工場に行きやすくなった』こと、そして人は『SNSの普及で口コミが広まりやすくなった』です。
これで、地方の工場を発掘してファクトリーブランドを作り出し、商品をネットで売って、SNSで広めてもらう、という流れがイメージできました」
もっとも、工場の開拓は想像以上に難しかった。
前述したように、工場は実績をほとんど表に出さないので、山田氏には、どこによい工場があり、どこに腕のいい技術が眠っているか分からなかった。
そこで、夜行バスでアパレル工場の集積地に行き、電話ボックスにあるタウンページで工場を探しては、片っ端から電話をかけた。そして「ファクトリーブランドを立ち上げ、ネット通販で売る」ことを持ちかけたと言う。
「けれど5ヶ月間は誰もまともに取り合ってくれなかった。僕自身にアパレルのものづくりの経験がなく、サイトが未完成だったことも、不信感につながった面もあって」

ある産地では「怪しい男がうろついているのでご注意を」と町内放送をされたこともあるそうだ。工場の入口にいた人と目が合った途端にドアの鍵をピシャっと締められる……。さすがの山田氏も帰りの夜行バスでは、悔しさのあまり一睡もできなかったと言う。
「しかし流れる景色を眺めながら考えるうちに、自分が思い違いをしていることに気づきました。『工場のために苦労している』などと上から目線になっていましたが、おこがましい話。ファクトリーブランドを作るのはあくまで自分の夢であり、工場の方にはその夢に付き合ってください、とお願いするのが筋では、と考えたのです」
「一緒に自分の夢を追いかけてもらえませんか」。そう頭を下げるようになると、事態は動いた。熊本のHITOYOSHIの経営者が快諾してくれたのである。同社はポール・スミスをはじめ、世界のさまざまな高級ブランドのシャツを手がける日本屈指のシャツ工場だ。山田氏の真摯な姿勢が、思わぬ大物の心を動かしたわけだ。
二人三脚の高級ワイシャツづくり。専門知識のない山田氏も、1万7000人のワイシャツの柄を街頭調査し、どんなシャツが良いか、明確なイメージを伝える努力をした。何度もの試作を得て完成したのが、今も販売しているワイシャツだ。
「『これまで企画したなかで最も品質の良いシャツができた』と言われ、涙が出た」
HITOYOSHIが「ファクトリエ」と組んだニュースは、すぐさま業界に広まった。それが信用になり、協力してくれる工場が増加。ラインナップが増えるにつれ、質の高い洋服がリーズナブルに買える、とファンも増えた。
工場を開拓し、お客様に商品を販売するなかで、山田氏が実感したのは、情熱を持つ重要性だ。
「自分や従業員だけが情熱を燃やすだけでは足りません。工場の皆さんにも熱狂していただくことが必要です。そうでないと質の高い商品づくりはできないし、お客様にも見透かされる」
工場で働く人々の情熱を引き出すために、「ファクトリエ」は、必ず、商品名に工場の名を出す。『Factelier BY ○○○(工場名)』、もしくは工場のブランド名だけ、といった具合だ。さらに「こんな商品をつくりたい」と細かく要望するのではなく工場側につくりたい商品を提案してもらうようにしている。

「自社の名前がついたブランドで、自ら生み出した商品なら『自分たちの商品』という意識を強く持つことができ、商品づくりに身が入る。自分たちのものづくりについてプライドを持って堂々と語れるようにもなります」
工場の人々の心を燃やすには、それだけではまだ足りない。長年、下請け仕事を続けていると、受け身の姿勢が染み付いてしまい、新しい仕事に挑戦したり、アイデアや意見を出したりするのに消極的になりがちだ。オリジナリティのある商品を開発するには、活発にアイデアが出るように、従業員の主体性を取り戻す必要がある。
そこで山田氏は、工場と契約する時、必ずあることをお願いする。「従業員同士で内省をしてもらうこと」だ。
「何をつくっているときが最も生きがいを感じられるのか。この工場がどうなれば嬉しいか。そうしたことを工場の皆さんで考えていただきたいのです。すると自分たちの理想の姿に向かって歩いていこう、という考え方が芽生え、志と主体性を持って商品づくりに挑んでもらえる」
残業ができない人もいるので、内省する時間は昼休みしかない。そこで昼休みは自宅に帰って食事を取るのではなく、工場で一緒に昼食を取ってもらうようお願いしている。山田氏の提案に乗り、多くの工場が実施しているそうだ。
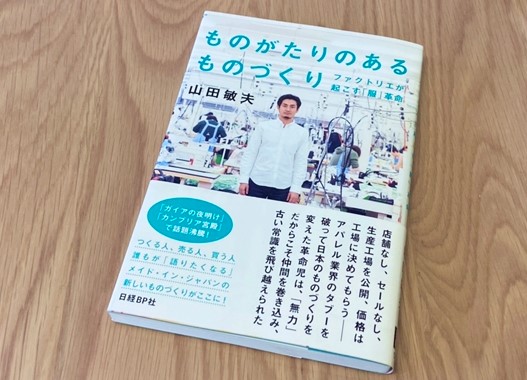
「ファクトリエ」の着想から誕生、成長の歩みをまとめた著書『ものがたりのあるものづくり』(日経BP社)。多くの仲間、工場、お客様との関係をどのように構築してきたのか、業界を問わず、経営者にとって貴重なストーリーが凝縮されている。
お客様に支持される商品をつくるためには、「技術」と「モチベーション」に加えて、「トレンドやニーズを敏感に察知し、形にするセンス」も必要だ。地方の工場で働いていると、都心部のトレンドに接する機会が持てないので、なかなかそのセンスが磨かれにくい。結果、マーケットを度外視したプロダクトアウトの製品ができあがることが少なくない。
そこで「ファクトリエ」では、毎週、銀座の百貨店やセレクトショップをまわり売れ筋やトレンドを調査。詳細なレポートを、工場が自由に見られる専用サイトにアップしている。
また、オリジナルブランドの商品づくりを始めた当初には、パターンやデッサンも提供している。だからこそ、高品質でトレンドもふまえた「売れる商品」が生み出せるわけだ。
すでに述べたように、お客様からの応援メッセージが工場に届くことも、裏方に徹していた工場にとって、何よりも嬉しく誇らしいことだろう。こうして工場はますますモチベーションを高め、良い商品ができ、お客様が喜ぶ好循環が生まれている。
ファクトリーブランドをつくるにあたって必要なことは、価値ある商品づくりだけではない。人間性も重要なカギ。山田氏はそう考えている。
「電話対応の仕方、銀座や熊本などにある店舗の掃除の状況、サイトやSNSでの対応……。自分たちの行動は360度、お客様に見られています。そういった一つひとつの行動からにじみ出るものによって、お客様からの評価は決まると考えています」
そこで山田氏が意識しているのは、自分自身が率先して人間性を磨き、視座を上げることだ。
視座を上げるために重要視しているのは、本と人。本は、移動中にKindleの読み上げモードで聞くことを習慣づけている。人に関しては、著書を読んでお会いしたいと思った方に手紙を書き、サイト上での対談企画や「ものづくりカレッジ」という勉強会での講演をお願いしていると言う。
相手はアパレル業に限らない。最近では、吉野での千日回峰行をやり遂げた現役唯一の僧侶である塩沼亮潤氏や、医師でありながら伝統芸能にも明るく、芸術祭の芸術監督も手がける稲葉俊郎氏などの講演や対談を実現している。

医師でありながら、芸術監督も務める稲葉俊郎氏と。
「印象深かったのはお2人とも『今の世の中は個のことばかりが言われすぎているのではないか』と指摘していること。そういう話を聞き、互いに支え合うことを考えることがますます大切だと感じています。こうした方のお話から学び続けることで、視座が高まっていくと考えています」
現在は新型コロナウイルスの影響が軽微とはいえ、今後はWithコロナ社会への対応を迫られることになるだろう。山田氏はどう考えているのだろうか。
「先のことを見通すより、『今に集中する』ことが大切だと考えています。これは、虎屋17代当主の黒川光博社長に教わったこと。虎屋はなぜ何百年も続いてきたのか、とたずねたところ、『伝統を守るのではなく、今に集中してきた』とおっしゃっていました。そうして、今のお客様が何を求めているかにフォーカスすれば、必要なことが見えてくるというわけです。私たちも、今のお客様が喜ぶことをしていけば、きっと続いていくし、その結果が、何十年、何百年と続くファクトリーブランドになる」

今に集中することは、自分の内側を熱狂させ、余熱を出し続けることにもつながるだろう。地方の工場に自由に足を運べない今でも、山田氏は、オンラインで工場に訪問し、新たなファクトリーブランドを発掘し続けている。その積み重ねが、未来につながっていくと信じている。

vol.56
DXに本気 カギは共創と人材育成
日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社
代表取締役社長
井上裕美


